ラピリジャパン株式会社のラピリブログ
日常のことから仕事の話題まで、ラピリジャパン株式会社の情報が盛りだくさんです。
最近の日記
10年越しの技術
我々が10年間一度も公式の場で受注したことのない技術を昨年特許申請いたしました。試験吹き付けをしている現場で、作業員の親方が「とっくにこの技術は辞めたものだと思っていた」とポツリ言葉を漏らしたのでした。私も相方も一度とてあきらめてはいない技術の醸成がとうとう特許申請、そして先日ある方から技術の打診があったのです。技術屋人生の真骨頂の出来事です。建築分野においてラピトモ住環境部会の会長からラピリの吹き付け技術の完成を求められていて2回試験吹きをしてみた結果、その配合が今まで足踏みしていた法面吹き付け技術につながるヒントを与えてくれたのでした。住環境部会の会長はまだ30代なのに「経験において無駄なことはなにひとつない」と言い切る男で、彼の発言にはいつも頭が下がる思いです。なんにせよ、ひとつの前進です。着実に技術を履行できる体制作りが急務です。
野生ラン

標題の野生ランの中でも目立たないカキラン、柿色なのでそういう名称になったのでしょう。研究所の「あすかの池」(通称ですが、、。下の子の蛙などの捕獲場所です。)のそばに他の場所で採取したものを移植したものです。生態を考えた場所に植えたので元気です。しかし、急速には繁殖しません。大きな草の中にひとつ柿色の花をつけた小さな草を見つけたときの爽やかな嬉しさはたとえようがありません。日本の植物はとても微妙な植生ですのでこの自然をどのように守ればいいのでしょうか?今西錦司先生は「保護された自然は自然ではない」という名言を残されましたが、今日絶滅危惧種がこれだけ多くなってきている現実をどう考えればいいのでしょうか?これからの自然保護の難しさを憂えてます。
酒蔵「刈穂」


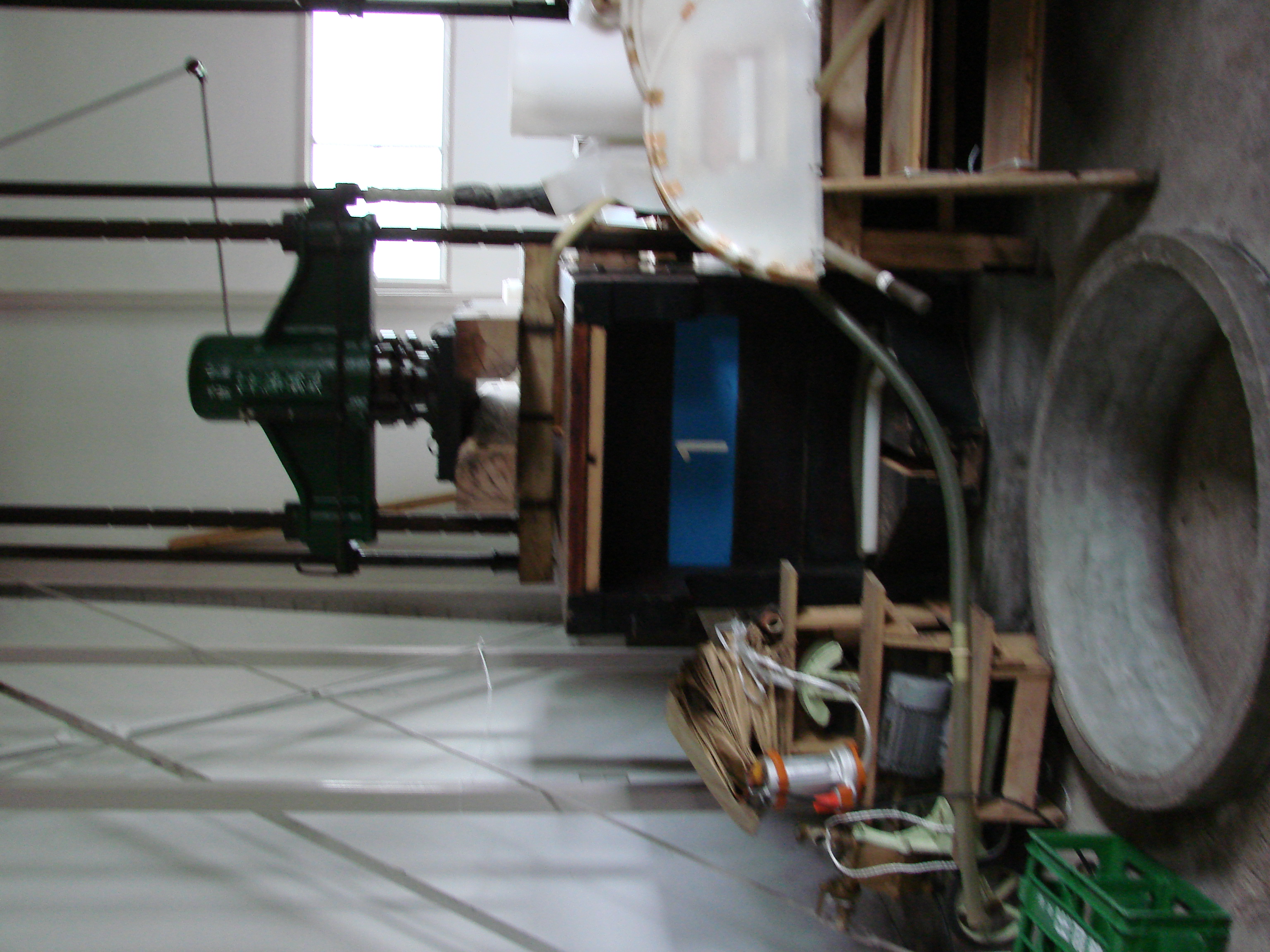
だいぶご無沙汰してしまいました。学会への応募書類の作成やら、技術発表会の資料作り、七夕オペラのワイン会と行事続きで書く暇がありませんでした。さて、先週土曜日に秋田清酒の伊藤社長の好意でオペラ歌手とともに刈穂の蔵を見学させていただきました。一同いろいろな感激がありましたが何といっても小生は社長の仕事にかける並々ならぬ熱意と言うものを感じました。後で製造部長に伺ったのですが、(この方は私の出来のいい後輩です)手作りの味に拘っているそうです。隅々まで気配りの利いた蔵をみて社長の姿勢を実感しました。写真は蔵のなかみです。「六舟」という吟醸酒のいわれは六つの舟(酒を絞る容器)という意味だそうで著名な作家水上勉の書がありました。それについては次回述べます。仕事の手本がこんな身近にあるとは。目からうろこでした。
時の流れ
今回の仙台出張はあることにエントリーしてしまったので、短期間に書類をまとめなければならない事態になりました。たくさんの方の助成が必要なため、いろいろお願した方々に敬意を表するための行動でした。回って歩いて気がついたことは、自分の友達は概して
このわがままな男に惜しみない協力をしてくれているという事実です。会社を設立して十数年が過ぎました。仕事上のパートナーはずいぶん変わりました。が、メンバーのハートは設立当初も今もいつも同じいい雰囲気です。大人として自立した方たちの集まりなので変な気を使わなくてもいいことがとても心地よいのです。我々が生まれた昭和20年代、少年時代だった昭和30年代はまるっきしのアナログの時代でしたが意志の疎通が図られていた時代でした。長田弘の詩集に「深呼吸の必要」というのがありますが、小生は自分より若い可能性豊な方にいつもこの本を読むことを勧めています。作者は我々よりだいぶ歳をとった方ですがその方の人柄を感じるとてもいい本です。小生に興味があるのでしたら「ラピリ」はこの本が一つの手本と表現しておきましょう。


